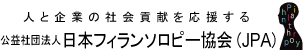Date of Issue:2023.10.1
◆ 巻頭インタビュー/2023年10月号

https://www.ikunotabunkaflat.org

https://www.ssi.osaka-u.ac.jp/
大学シンクタンクとNPOの共創
特定非営利活動法人IKUNO・多文化ふらっと理事・事務局長
宋 悟 さん
大阪大学社会ソリューションイニシアティブ長・大学院経済学研究科教授
堂目 卓生 さん
大阪市生野区は、外国籍住民が2割を超える言わずと知れた「大阪コリアタウン」。この場所に2021年、廃校になった小学校の跡地を活用した多文化共生の拠点「いくのパーク」が誕生した。運営するのは、特定非営利活動法人IKUNO・多文化ふらっと(以下、多文化ふらっと)と株式会社RETOWN。関わるのは大阪大学のシンクタンク、社会ソリューションイニシアティブ(以下SSI)である。現場に足を運び、多文化ふらっと事務局長の宋悟さん、SSI長で経済学者の堂目卓生さんに話を聞いた。
「当事者」として目覚めた瞬間
― 「いくのパーク」は、多文化共生の拠点として、場づくりや子どもの支援にとどまらず、食、スポーツ、観光、ダンス、アートなど幅広い事業を展開しているのが印象的です。宋さんはそもそも、どんな経緯や思いで多文化共生の取り組みに関わってこられたのでしょうか?
宋 ここは100年以上前から、在日のコリアンと日本人の共生の歴史がある地域です。私はここに住んで30年以上経ちますが、今はニューカマーが増えてきました。今後10年、20年経つと、ますます多文化共生は切実な課題になり、それに伴って、生まれてくる子どもの貧困も深刻になります。そんな中で、2019年に多文化ふらっとを立ち上げました。「市民主導で多文化共生の拠点を立ち上げたい」と思っていた頃、再編に伴う小学校の跡地利用の公募プロポーザルがあったんです。設立間もない小さな法人でしたが、SSIを含めいろいろな方に参画してもらって、手を挙げました。
― 法人を立ち上げるまではどんなことをされていたのですか?
宋 私は三重県出身の在日コリアン3世なのですが、高校生の頃は在日コリアンというアイデンティティはありませんでした。どちらかというと、恥ずかしかったし、周囲にもどこか隠していました。でも大学に入った1980年頃、韓国では民主化運動が高揚していたタイミングでした。「膝を屈して生きるより、立ったまま死のう」というスローガンを掲げて身を粉にして闘っている韓国の大学生たちを見て、カルチャーショックを受けたんです。そこで、私の人生が決まりました。その後は、在日の団体に所属して、デモや集会、ハンガーストライキなどにも参加しながら、社会活動家として生きてきました。
― 「当事者」として骨太な活動を続けてこられた宋さんのような方が関わる団体が、ある意味で中立的なSSIのような外部団体と手を組むことは、新鮮に映ります。
宋 ここは学校全体を活用した拠点で、事業規模も大きいので、当初からNPOの力だけでは難しいと感じていました。自分たちだけでやることに固執すれば、「生野区を全国ナンバーワンのグローバルタウンにする」という私たちの理想は夢物語になってしまう。だからこそ、いろいろな職種、セクターの人と手を結ぼうと思いました。
大学が市民社会に関わる

堂目 一度、宋さんが大学まで来てくれたんです。「小学校が廃校になって、跡地活用のコンペがある。有力な企業が参画し、競合相手もいるから、採択されるためになんとか関わってくれないか」と提案されたのが、最初の出会いです。話を聞いたとき、ボトムアップ的に社会活動をしている点が印象的でした。助けを必要としている人たちと共に社会を創っていこうというのがSSIを立ち上げたときの大きな方針だったので、一緒にやりましょうということで連携が始まりました。
― SSIはどのような経緯で立ち上がったのでしょうか?
堂目 2015年に経済学部長になった時、文系不要論がいろいろな方面から聞こえてきました。自然科学は世の中の役に立っているけれども、社会科学や人文科学は役に立っていないのではないかということで、教育学部をはじめ存続が問われる事態になっていた。そんな時期に経済学部長をやっていて、「えらいことになってきた」と感じていたんです。
日本は明治維新以降、哲学や歴史、法学など人文学や社会科学が背骨になる考え方を作ってきたはずなのに、国の礎である学問をなぜ軽視するのかと。でも一方で大学を見渡せば、研究者の多くは非常に狭い世界の中で仕事をしている。社会は課題だらけなのに、先人に比べて、身体を張って社会に関わっているだろうか。学問同士が横でつながっているだけではなく、現場を巻き込んで、共に課題解決に取り組むべきではないのか。そんな問題意識をもって、未来社会を構想するシンクタンクとして2008年にSSIを立ち上げました。
多文化ふらっとのオープニングセレモニーにも参加しました。いろいろな活動が立ち上がっていますが、K-POPのダンススクールは成功しそうですね(笑)。
日本は明治維新以降、哲学や歴史、法学など人文学や社会科学が背骨になる考え方を作ってきたはずなのに、国の礎である学問をなぜ軽視するのかと。でも一方で大学を見渡せば、研究者の多くは非常に狭い世界の中で仕事をしている。社会は課題だらけなのに、先人に比べて、身体を張って社会に関わっているだろうか。学問同士が横でつながっているだけではなく、現場を巻き込んで、共に課題解決に取り組むべきではないのか。そんな問題意識をもって、未来社会を構想するシンクタンクとして2008年にSSIを立ち上げました。
多文化ふらっとのオープニングセレモニーにも参加しました。いろいろな活動が立ち上がっていますが、K-POPのダンススクールは成功しそうですね(笑)。
宋 そうですね。もともと教室だった部屋を鏡張りにして、ダンススクールを始めます。国籍やルーツも関係なく、K-POPを踊りたい若い子たちが集まって、「K-POP」という、いまや誰もが共有できる文化の下で交流し
てもらいたいという仕掛けです。
シンクタンクが「現場」と交わること
― 「現場」を担う宋さんにとって、大学発のシンクタンクであるSSIとの協働によって、どんな良い影響があったのでしょうか?

イベントを開催
宋 やはり、私たちが大事にしなければならないのは「現場」です。常に、具体的な現実が目の前にある。例えば、私たちの運営する学習支援拠点に、タイにルーツのある高校生が来ていました。彼女は日本人の父とタイ人の母のもとタイで生まれ、両親の離婚後、日本語を勉強したいと一人で日本に来た。それで学校の先生を通じて、私たちの施設を訪ねてくれたのですが、コロナ禍の中、高熱が出る病気に罹ってしまった。ある夜、僕が訪問することになり、簡単な食事と、少しばかりのお金を渡して帰ったのですが、その帰り道、お恥ずかしい話ですが、還暦過ぎたおじさんは号泣してしまいました。私のハルモニ(おばあちゃん)が日本に来たときと同じ状況じゃないかと悔しくて・・・。
頼れる人がいない中で、一人きりでがんばっている。その子はタイで起業する夢を持っているんですが、家族からは大学なんて行くなと言われ、お金を無心される。才能あふれる子どもが、そういう立場に置かれている。そこには極めて具体的で切実な社会の現実があり、それは100人いれば100通りあるんです。
頼れる人がいない中で、一人きりでがんばっている。その子はタイで起業する夢を持っているんですが、家族からは大学なんて行くなと言われ、お金を無心される。才能あふれる子どもが、そういう立場に置かれている。そこには極めて具体的で切実な社会の現実があり、それは100人いれば100通りあるんです。
― 現場に身を置いているからこその言葉ですね。
宋 はい。ただ一方で、目の前の現場に集中するあまり、団体としての大きな方向性を思考したり、自分たちの活動を大きな文脈で位置づけるのが苦手な面もあります。だからこそ、シンクタンクに関わってもらいたい。医療、福祉、介護などのエッセンシャルワーカーと呼ばれる人たちの存在は、AIでは代替できません。
「どう生きるのか」を正面から扱う人文学・社会科学が復権する時代は、必ずくると思います。だからこそ、日本にはこれまで根付かなかった市民発の骨太のシンクタンクが求められる。しかし、行政や企業がやるとどうしても回りくどくなります。そう考えると、意外と大学は、市民社会に近いシンクタンクの役割を果たせるのではないでしょうか。
「どう生きるのか」を正面から扱う人文学・社会科学が復権する時代は、必ずくると思います。だからこそ、日本にはこれまで根付かなかった市民発の骨太のシンクタンクが求められる。しかし、行政や企業がやるとどうしても回りくどくなります。そう考えると、意外と大学は、市民社会に近いシンクタンクの役割を果たせるのではないでしょうか。

堂目 多文化ふらっと以外にもたくさんの現場と関わっていますが、現場はまさに命がけで一つひとつの現実と向き合っています。そこに研究者という立場で関わる私たちの距離感も難しい。なるべく客観的・俯瞰的に記述しようとしていますが、綺麗にまとめようとすればするほど、現場の物語が抜け落ちてしまうんですね。一方で、現場に近づきすぎれば言葉を失ってしまう。
現場で見聞きしたことを制度や政策に反映する動きも必要ですが、具体と抽象、個別と全体、それらを往復し続けながら、できること、すべきことを考え続けていくしかない。いわゆる大手のシンクタンクのように、提言や事例をズラっと並べられるかというと、そんなに簡単にはいきません。
現場で見聞きしたことを制度や政策に反映する動きも必要ですが、具体と抽象、個別と全体、それらを往復し続けながら、できること、すべきことを考え続けていくしかない。いわゆる大手のシンクタンクのように、提言や事例をズラっと並べられるかというと、そんなに簡単にはいきません。
シンクタンクに問われるセンス
― 目に見える結果がすぐに出なくても、SSIのような中間組織が現場に関わり続けることには大きな意味がありますね。
堂目 私も最近そう感じ始めています。ある事業を評価するうえでは、KPI、KGIなどいろいろな方法があり、「社会実装につながったのか? 役に立ったのか?」という外からのプレッシャーの中で、分かりやすい成果
が出ていない状況をもどかしく思うこともあります。でも5年間続けてきて思うのは、SSIという場があることで、すぐに具体的に役立つわけではなくても、現場から見える社会を、言葉にしながらつないでいくことはできる。
宋 そういう意味では、シンクタンクには現場と関わるうえでの「センス」も問われますよね。地域の課題は複雑に絡み合っていて、社会の状況も日々刻々と変わる。目に見えるものだけを評価するようなスタンスでは、事の本質を見逃してしまう。数値や客観性では測りきれないものもきちんと補足し続ける。そのバランスこそが、シンクタンクには試されているのではないでしょうか。

いくのふらっとだいがくシリーズ
「多文化共生と表現活動」vol 1.
「生きることばを紡ぐ」
堂目 今は、誰もどこへ向かえばいいのか分からない時代です。だからみんなで考えるしかない。大学を出ていようが出ていまいが、健康だろうが病弱だろうが、みんな不安を抱えている。エリートだって実は脆弱で、自分を枠の中に位置づけて納得しようとするけれど、本当にそれでいいのか不安な気持ちを持っている。バルネラビリティ(vulnerability/弱さ、もろさ)を抱えているという意味では、みんな同じです。
宋 明確なゴールに向かっていく時代は終わって、ゴール自体がどこか分からない時代ですよね。単純化、効率化の誘惑にかられますが、複雑なものは複雑なまま受け止めるしかない。
― 現場で一人ひとりを支援する中でも、そうした社会の変化を感じることはありますか?
宋 今後、子どもたちへの教育的サポートの充実のため、多言語の相談窓口を開設しています。そこにやってくる厳しい状況に置かれた子どもたちと関わると、背後に、保護者の生活課題が見えてくる。保護者の暮らしが安定しないと、子どもも救えない。でも家庭環境自体を変えるのは、簡単なことではありません。アウトリーチ型の支援で、相談援助のスキルを磨いて困っている人に知識を与え、法制度につなげていくなど、やれることはあるとは思いますが、どうやってもすぐには解決しない。5年、10年、下手をすれば20年かかるケースが実に多い。そういうソーシャルワークがどんどん増えていく。
だから私たちのような小さな団体が手触り感をもって進めるには、12万人強が暮らす生野区くらいがちょうどいい。ローカリズムの井戸をどんどん掘って、均質化する世界の流れに対抗するロールモデルを担っていきたいと思っています。
だから私たちのような小さな団体が手触り感をもって進めるには、12万人強が暮らす生野区くらいがちょうどいい。ローカリズムの井戸をどんどん掘って、均質化する世界の流れに対抗するロールモデルを担っていきたいと思っています。
堂目 ローカルにやらないと、実のある実践にはならない。現場で深められたものを、シンクタンクが拡げていく。そういう作業の繰り返しかなと思います。
― ローカルで民主主義を起動する

いくPAの図書室~ふくろうの森~
宋 マイノリティを変えると同時に、マジョリティも変えないといけないですよね。自治体の多文化共生の制度づくりを、当事者が主体になって作っていけたらとは考えています。多文化共生については、「多文化共生基本法」のような基本法が存在しないので限界はありますが、自治体の単位でできることはあるはずです。ただ、自治体に計画をつくっていくだけのエネルギーや経験値はない。それを批判するだけではなく、じゃあ一緒に作りましょうと。1つでも2つでもアクションプランをつくることが理想です。
堂目 市民と行政が一緒にまちをつくっていく、本来の民主主義ですよね。偶然と戦略性を同時に生かしながら、いろいろな関係者が主体性を持って関わる機運が、ローカルに生まれていくことが大事です。
― 地域を本気で変えようとするときには、関係者からの反発もあったりするのでしょうか。
宋 地域社会は、まだまだ旧態依然としている面があります。何か大きな変化を興そうとする時、影響力のある一部の年配の方たちから「その話は○○さんを通したか?」「お前たちに本当にできるのか?」と、地域ならではの政治性や慣性の法則が働くことも珍しくないです。企業でも行政でも起きていることだと思いますが、これからは異質なものを包容していく、危うさや混沌さを抱きしめながら、前に進む勇気が必要です。

堂目 多様性を持ちながら前に進むには、強烈な共通性が必要だとも思います。これまではそれが「民族」だったのかもしれませんが、これからは「人類」や「命」を共通項にするしかないと思っています。「SDGs」にはいろいろな批判もありますが、世界全体で「これしかない」というよりどころを持ったという意味では、とても価値のあるスローガンです。人間は「Human Being」ですが、「Being」つまり「あるだけでいい」という考え方や場所が求められていると思います。「Doing」=何かすること、役に立つことが常に求められてきた近代から抜け出そうという意味です。
宋 逆説的ですが「みんながいるだけでいい」という場を作っていると、自然と皆それぞれに自分の役割を見つけていくんです。今は子ども食堂や教育支援など、150人を超えるボランティアが関わっていますが、この事業をしていて一番おもしろいのは、関わる人たちが勝手に「自走し出すとき」なんです。2022年に大きなフェスをやりましたが、中学生、教員、大学生、企業の社員も関わってきて、いちいち事務局から指示していられない状況になったので、役割やスケジュールなど大枠だけ決めて、あとは自由にさせたら、みんな主体的に動きだしたんです。社会活動家としては、そんな瞬間が非常にうれしいですね。
堂目 歴史研究の結論のひとつは、「歴史は無数の無名の人たちがつくってきた」ということです。教科書では、ルターが宗教革命を、ワットが産業革命を起こしたと学ぶけれども、その人が一人で時代を変えたわけではありません。記録にも残らない一人ひとりの動きが積み重なり、あるタイミングで、象徴的な誰かの力で100年変わらなかったことがガラガラッと変わるわけです。ソーシャルアクションは、成果がすぐに見えるわけではありませんが、100年後、200年後に向けて、誰かがバトンをつないでくれる。社会変革自体は、自分の目では見られないことがほとんどです。だからこそおもしろいし、それを信じて続けるしかないんです。
【インタビュアー】
公益社団法人日本フィランソロピー協会
理事長 髙橋陽子
(2023年8月18日 特定非営利活動法人IKUNO・多文化ふらっと にて)
公益社団法人日本フィランソロピー協会
理事長 髙橋陽子
機関誌『フィランソロピー』巻頭インタビュー/2023年10月号 おわり